「セミナー物理基礎+物理」について,特徴や難易度,実際に使ってみた使用感を紹介します。
この記事でわかること
- セミナー物理の特徴・難易度
- セミナー物理のメリット・デメリット
- セミナー物理を実際に使ってみた使用感
- セミナー物理の使い方
セミナー物理の特徴
| 項目 | 評価 |
|---|---|
| 分類 | 網羅系問題集 |
| 難易度 | |
| 分量 | |
| わかりやすさ |
セミナー物理は主に高校で配布される教科書の傍用問題集です。
公式を使うだけの基本問題から,東大の過去問(ある程度易しく改題されていますが)までを956問という大量の問題数でカバーする物理の網羅系問題集です。
 あんとら
あんとら力こそパワー!みたいな問題集です
問題数が多いので当然問題の種類も多種多様です。
問題の例
- 多くの人が躓きがちな「ベクトルの分解・力の図示だけをする」問題
- 「運動方程式の立式だけする」問題
- 共通テストを意識した図表や会話文から設問内容を読み取るようないわゆる「思考力問題」
- 二次試験に出てくるような本格的な難問
セミナー物理の対象レベル
初学者~旧帝大除く国公立大学あたりがセミナー物理の対象範囲です。
基本的にこの1冊を全部解けるようにすれば物理の学習で困ることはないでしょう。



旧帝大以上の難関大を目指す場合,名問の森や重要問題集に更に取り組めば良いと思います
セミナー物理のメリット・デメリット
セミナー物理を使ってみて感じたメリット,デメリットを紹介します。
セミナー物理のメリット
セミナー物理のメリット
- 物理の圧倒的な基礎学力がつく
- 有名な典型的問題が一通り網羅されている
- 学校配布の王道な問題集なので少なくともハズレではない
セミナー物理の最大のメリットはやはり圧倒的な網羅性です。
セミナー物理に出てくる問題を抑えると,全統記述レベルの模試や定期試験で出てくる問題は典型的な操作として頭を使わずに処理できるようになります。
また,学校で配布される問題集なので少なくとも「ハズレ」な問題集ではありません。
物理の問題集は何やっていいかわからない方は,セミナー物理(or類する教科書傍用問題集)をやれば,まず間違いはないでしょう。



合う合わないはあると思うので一回見てみることをおすすめします
セミナー物理のデメリット
セミナー物理のデメリット
- とにかく分量が多い
- 解説がやや簡素でわかりづらい
セミナー物理の最大のデメリットはとにかく分量が多いことです。



網羅系問題集のいいところがそのまま裏目に出ていますね…
分量に関してはこの1冊を解けば大学入試物理で困ることはほぼ無くなるので良いのでは…と思います。
一方で,解説が簡素なのは仕方ないとはいえ見逃せないデメリットですよね。特に物理は慣れないうちは全くわからない科目なので。
セミナー物理のオススメ使い方
セミナー物理は分厚い問題集ですが基本的な解き方はシンプルです。



実際にやった使い方を期間も含めて紹介します
Step1:問題をすべて解き解ける問題と解けない問題を仕分ける(4ヶ月)
まずは掲載されている問題をすべて自力で解いてみましょう。
セミナー物理は
- 基本例題
- 基本問題
- 発展例題
- 発展問題
- 総合問題
という5段階の構造をしています。
解き方は基本的にイチから全て解く使い方で問題ありません。



問題集は解けない問題を解けるためにするためのものであるので,この段階で問題が解けないことは全く問題ありません
そのときのポイントとして解けなくてもすぐに諦めて答えを見ずにできる限り時間をかけて取り組んでみる事を意識すると良いでしょう。
粘り強く取り組んでみて,どうしてもわからなかったら諦めて解答・解説を見ましょう。
解説を読むときのポイント
- 自分が解けなかった原因(必要な公式を知らなかった?,その分野の理解不足? etc)を分析する
- 次同じ問題と出会ったときにどういうアプローチをすれば解けるようになるかを考える
また,問題に取り組んだときの日付を書いておくと後から見返すときに便利です。
自力で解けたら◯マークをその問題番号の自分で見てわかるところに書いておきましょう。
解けなかったら同様に,✕マークを書いておきましょう。
Step2:解けなかった問題を解けるようにする(3ヶ月)
すべての問題を解いた時点で最低限の基礎学力はつくでしょう。
しかし,更にレベルアップをするためにStep1で✕マークを付けた問題をもう一度解き直してみましょう。



この過程は正直めちゃしんどい(解けなかった問題ばかり扱うから当然)
しかし,一番自分の基礎学力がつくStepでもあるので諦めずに頑張りましょう。
ここでも,解けた問題は◯と日時をつけ,解けなかった問題はまた✕マークと日時をつけましょう。
あとはこのサイクルの繰り返しです。
8~9割の問題が自力で解けるようになっていたら,物理の基礎学力はお釣りがくるほどつくでしょう。
セミナー物理が終わったら
セミナー物理の問題をすべて解ききることが出来たら,相当の物理の基礎学力がついています。
あとは志望大学のレベルに合わせて何をやるか検討しましょう。
次にやるべきこと
- 私立大理系~旧帝大を除く国公立大学志望の方
→これ以上新しい問題集に取り組む必要はありません。他の科目に取り組む&物理に関しては赤本を解いてみましょう - 旧帝大以上の難関大(or医学部等)を目指す方
→名問の森や重要問題集といった入試問題集に取り組んでみましょう
まとめ
この記事では
- セミナー物理の特徴・難易度
- セミナー物理のメリット・デメリット
- セミナー物理を実際に使ってみた使用感
- セミナー物理の使い方
について紹介しました。参考になれば幸いです!
他の参考書も紹介しています!
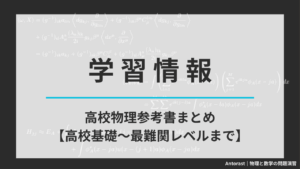
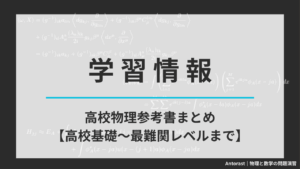
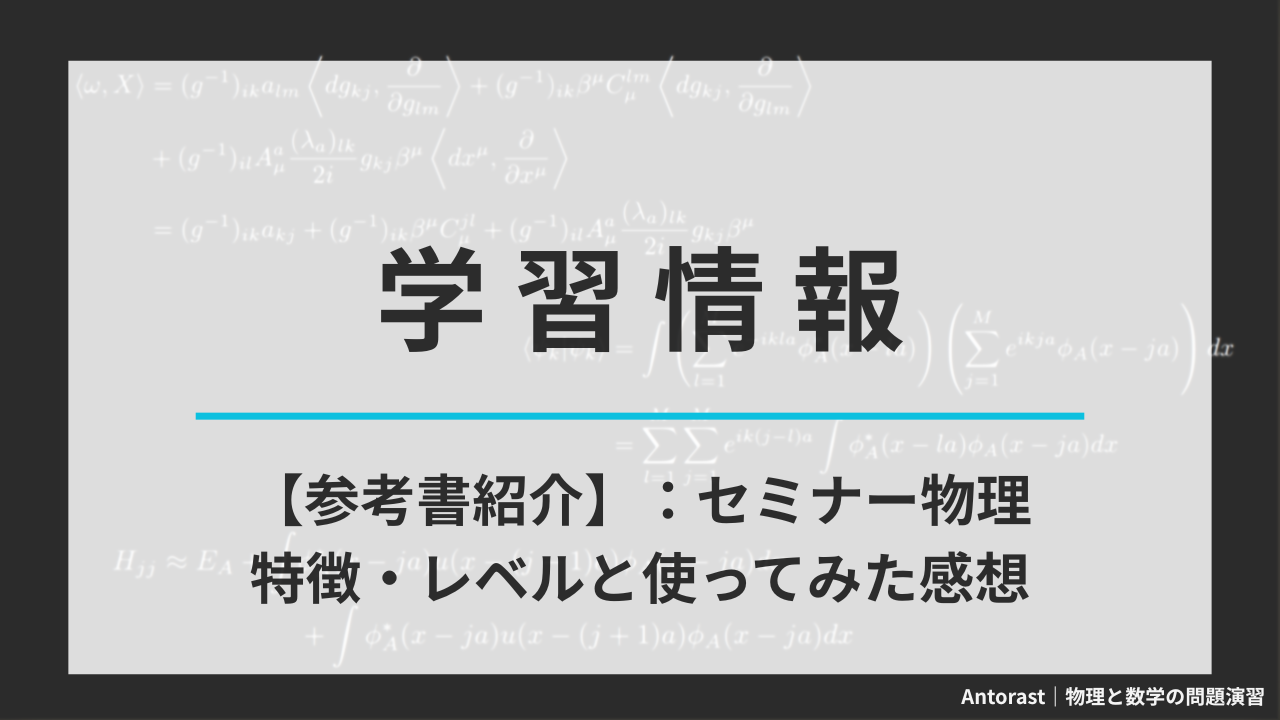

コメント